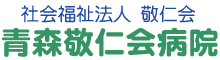病院概要
名 称 |
社会福祉法人 敬仁会 青森敬仁会病院 |
|---|---|
所在地 |
〒039-3502 |
電話番号 |
017-737-5566 |
FAX番号 |
017-752-2151 |
理事長 |
丹野 智宙 |
院長 |
曽我 須直 |
診療科目 |
内科・リハビリテーション科・整形外科 |
病床数 |
120床 |
施設基準 |
回復期リハビリテーション病棟入院料(4) |
医療安全管理指針について |
120床 |
施設基準について
当院は、厚生労働大臣の定める施設基準について東北厚生局へ以下の届出をおこなっています。
【基本診療料の施設基準に係る届出】
○回復期リハビリテーション病棟入院料4
休日リハビリテーション提供体制加算(2階2病棟)
当院の回復期リハビリテーション病棟では、1日に13人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と1日に8人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・朝8時30分~夕方5時まで、看護職員及び看護補助者1人当たりの受け持ち数は4人以内です。
・夕方5時~朝8時30分まで、看護職員及び看護補助者1人当たりの受け持ち数は15人以内です。
○療養病棟入院基本料1
夜間看護加算(3階3病棟)
当院の療養病棟では、1日に11人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と1日に11人以上の看護補助者が勤務しています。
なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。
・朝8時30分~夕方5時まで、看護職員及び看護補助者1人当たりの受け持ち数は4人以内です。
・夕方5時~朝8時30分まで、看護職員及び看護補助者1人当たりの受け持ち数は15人以内です。
○療養病棟療養環境加算1(3階3病棟)
○認知症ケア加算(加算3)
○診療録管理体制加算(加算3)
○データ提出加算(加算2及び4)
〇感染対策向上加算3
〇連携強化加算
【特掲診療料の施設基準に係る届出】
○CT撮影
○脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算)
○運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算)
○外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
○入院ベースアップ評価料27
【入院時食事療養等】
当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
【保険外併用療養費に関する届出】
特別の療養環境の提供(差額室料)
別表のとおり届出しています。
医療安全管理指針について
1.医療安全管理に関する基本方針
(1)医療提供にあたり、事故の発生を未然に防ぐことが原則であり、事故が発生した場合は、救命措置を最優先するとともに、再発防止に向けた対策をとる必要がある。本指針は、医療事故を未然に防ぎ、質の高い医療を提供することを目的に策定する。なお、本指針における事故とは、当院の医療提供に関わる場所で、医療の全課程において発生するすべての事故を指し、職員の過誤・過失の有無を問わないものとする。
(2)事故防止のための基本的な考え方
① 医療事故は起こらないことが当たり前である。しかし、人間は時に誤りを犯す生物であり、常に余裕を持ち医療事故を起こさないよう業務に当たることが大切である。
② 思いこみ、ウッカリミスの防止には、基本事項の確認・再確認と必要であれば二重、三重のチェックをする。
③ マニュアル、決まりの不履行や当たり前のことをきちんとしなくなったら、大事故発生の前兆と考えて対処する。
④ 同僚、上司のみならず、他部門、他診療科のアドバイスやチェックに素直に耳を傾ける。
⑤ 他人がしてくれるつもり、看てくれるつもりをあてにしてはならない。
⑥ 警報は常に鳴らない、接続は外れるもの、機器は故障するものという危機管理意識を持つ。
⑦ マニュアルだけでなく、常に業務全体を視野において、患者最優先の医療を心がける。
⑧ 患者とのコミュニケーションには十分配慮し、患者や家族への説明はその内容が十分理解されるよう心がける。
⑨ 診療に関する記録は明確に記載するとともに、上司・先輩・同僚のチェックを受ける。
⑩ 健康維持、研修、学習などの自己管理・自己啓発に常に留意して、体調不良時や不慣れな業務では特に慎重に行動し、必要がある場合は共同作業とする。
2.医療安全管理委員会の設置
(1)各部門の責任者により構成する医療安全管理委員会を設置し、次の医療安全管理対策について検討し、実施する。
① リスクマネジメントマニュアルの見直し
② インシデント・アクシデントの発生状況の把握と再発防止対策の検討
③ 医療安全に関する職員研修の企画
④ 医療安全情報の提供
⑤ その他医療安全に関する事項
(2)重大な問題が発生した場合は、委員会において速やかに発生の原因を分析し、改善策を立案・実施し、職員への周知を図る。
(3)委員会は、毎月1回程度定例的に開催するとともに、重大な問題が発生した場合は適宜開催する。
3.職員研修に関する事項
(1)研修は、安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について、職員に周知徹底を図ることを目的とする。
(2)研修は、医療安全管理委員会で計画を作成し、年2回程度定期的に開催するほか、必要に応じて開催する。
(3)研修は、当院の具体的な事例を取り上げ、全職員を対象として行う。
(4)研修を実施したときは、実施内容(開催日時、出席者、研修項目)について記録する。
4.医療事故発生時の対応
(1)アクシデント、インシデント発生時は、直ちに職場の長へ報告するとともに、事故当時者の安全確保を第一に考え、対応する。
(2)職場の長は、速やかにリスクマネージャーへ報告するとともに、リスクマネージャーは管理者へ報告する。
5.事故報告及び再発防止対策
(1)アクシデント、インシデントが発生したときは、「アクシデント・インシデント発生報告について」により、すべての事例について報告書を作成する。
(2)事故の報告は、診療録、看護記録等に基づき作成する。
(3)報告されたアクシデント、インシデントは、「インシデント・アクシデント発生状況」としてまとめて医療安全管理委員会へ報告し、内容を分析して同じような事例の再発防止のための手立てについて検討を行う。
6.情報共有及び相談に関する基本方針
(1)患者及び家族等と情報を共有するため、この医療安全管理指針を外来及び病棟掲示板に掲示し、閲覧できるようにする。
(2)病状や治療方針等に関する患者からの相談については、医療相談員が懇切丁寧に対応し、必要に応じて担当医等に内容を報告する。
7.その他医療安全の推進のための基本方針
(1)本指針は、必要に応じて改定を行うとともに、研修などを通じて職員に周知する。
(2)リスクマネジメントマニュアルを整備し、定期的に見直し改定を行っていく。